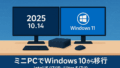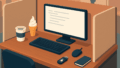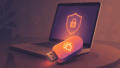ここで扱うのは,捨てる同然のPCである。内蔵ストレージのデータは未練ゼロ,動かなくても痛手なし,ダメもとで試す――この条件を満たすなら,私はUbuntu LTSのクリーンインストールで“再生”を強く勧める。Windows 7から10に無償アップグレードした古参機でも歓迎だ。
Ubuntu LTSは長期サポート版で,安定性と更新継続性が売りである。その中でも現時点の本命はUbuntu 24.04 LTS(Noble Numbat)だ。標準のUbuntu Desktopは5年間(~2029年4月)のセキュリティアップデートが提供され,必要なら有償のUbuntu Pro(ESM)でさらに延長できる。
この提案の狙いと限界
- 狙い:古いハードを捨てずに,ブラウジング,メール,簡単な文書作成,オンライン学習,写真の整理など“クラウドでおこなう作業”を気持ちよくこなす環境を作ること。
- 限界:Microsoft Office(デスクトップ版)を使う用途は不向きである。LinuxはOfficeのネイティブアプリをサポートしていない。ブラウザ版(Microsoft 365 for the web)で多くの作業はこなせるが,VBAマクロや高度なレイアウト,複雑なアドインなどは機能制限にぶつかる。業務がOffice中心なら無理にLinuxへ移さない判断も十分に現実的だ。
どのUbuntu LTSを入れるか:標準か,軽量フレーバーか
- 標準(Ubuntu 24.04 LTS,GNOME):新しめのCPU(第5世代以降)と8GB以上のRAMがあるならこれでよい。操作はモダンで,周辺情報も豊富。
- 軽量フレーバー(Xubuntu 24.04 LTS=Xfce,Lubuntu 24.04 LTS=LXQt,Ubuntu MATE 24.04 LTS=MATE):4GB以下や,第4世代以前のCPUにはこちらがおすすめ。こちらは3年サポートだが,体感の軽さが段違いである。
Intel世代別のおすすめ(目安)
※同じ世代でも個体差がある。SSD換装とRAM増設は最優先で検討する。
| 世代と例 | 想定年式 | RAM目安 | 推奨LTS | 理由と注意 |
|---|---|---|---|---|
| 第1~2世代(Nehalem / Sandy Bridge,例:i5-2400) | 2009–2011 | 4GB未満が多い | Lubuntu 24.04 LTS(最有力),Xubuntu 24.04 | LXQtやXfceは軽く,非力でもGUIが軽快。まずはSSD化で体感激変。フレーバーはサポート3年。 |
| 第3世代(Ivy Bridge,例:i5-3320M) | 2012 | 4–8GB | Xubuntu 24.04 LTS,Ubuntu MATE 24.04 | 省リソースで安定。動画再生や複数タブのブラウジングも実用圏。 |
| 第4世代(Haswell,例:i5-4570) | 2013–2014 | 8GB推奨 | Ubuntu MATE 24.04 LTS,標準Ubuntuも可 | SSD+8GBなら標準Ubuntuでも快適。軽量志向ならMATE。 |
| 第5~6世代(Broadwell / Skylake,例:i5-6200U) | 2015–2016 | 8GB以上 | 標準Ubuntu 24.04 LTS | ブラウザ中心なら余裕。外部モニタやPWAの常用にも耐える。 |
| 第7~8世代(Kaby Lake / Coffee Lake,例:i5-8250U) | 2017–2018 | 8–16GB | 標準Ubuntu 24.04 LTS | 現役レベル。GNOMEでのマルチタスクも安定。 |
32bit世代は非対象:現在,Ubuntu Desktopは64bitのみが提供される。極端に古い32bit専用機は対象外である。
ここまで読んで「本当に動くの?」という不安に答える
私の目安では,2GHz級のデュアルコア+4GB RAM+SSDでブラウジングとWebアプリは快適圏に入る。公式ドキュメントやコミュニティ情報でも,4GB RAM/25GB以上の空き容量が“現実的な最低ライン”として繰り返し示されている。ディスプレイは1024×768以上が目安だ。
準備するもの(最短チェックリスト)
- 別PC(ISOを落としてUSBを作るため)
- 8GB以上のUSBメモリ(インストーラ用)
- 有線LAN(初回セットアップでWi-Fiが不安定な個体の安全策)
- バックアップ不要の対象PC(ディスクは完全消去する)
ダメもとの再生企画なので,中のデータは全消去が原則である。
クリーンインストールのながれ(ざっくり)
- ISOを取得:公式のUbuntu 24.04 LTS(標準または狙いのフレーバー)をダウンロード。
- USBを作成:別PCでRufusやBalenaEtcher等を使って起動USBを作る。
- 起動順を変更:対象PCのBIOS/UEFIでUSB起動を最優先に。Secure Bootが古い機種で癖になるときは一時的に無効化。
- インストール:インストーラでディスクを消去してインストールを選ぶ。ネット接続を有効にすると,開始時点で基本アップデートが入って楽。
- 初期設定:日本語入力(Fcitx5やMozc),時刻同期,省電力設定(自動スリープ)を整える。
- 更新:最初の再起動後にソフトウェア更新を実施しておく。
何が“できる”のか:クラウド時代の主力ツール
- Gmail/Googleカレンダー:ブラウザからそのまま使える。通知はブラウザの通知機能を活用。
- Google ドキュメント/スプレッドシート:共同編集が主眼なら最適解に近い。
- Microsoft 365(Web版):Word/Excel/PowerPointの基本編集は可能。だがVBA/アドイン/高度な互換要求は壁に当たる。Officeが中核業務ならWindowsを残すのが正しい。
- Zoom/Meet:ブラウザ版で参加できる。
- Edge/Chrome系ブラウザ:Linuxでも入手でき,拡張機能やPWAで“ネイティブ風”運用が可能。
- PDF仕事:Evince等での閲覧,必要ならMaster PDF EditorやWebサービスで注釈もいける。
LibreOfficeの扱いと“Office前提”への正直なコメント
LibreOfficeはローカルに置く無料のオフィススイートとして優秀である。しかしレイアウト互換やマクロは完全ではない。企業・顧客とのやり取りが.docx/.xlsx前提なら,私の結論は一貫して「Web版Officeで足りるかを先に検証し,足りなければWindowsを併用」である。Linux一本で無理をしないほうが総コストは下がる。
体感を上げる“最後の一押し”
- SSD換装:SATAの2.5インチSSDでOK。費用対効果は最強。
- RAM増設:4→8GBで体感が大きく変わる。
- 軽量デスクトップへ切替:標準Ubuntuが重いと感じたらXubuntuやLubuntuへ。設定移行の手間より日々の快適さを優先する価値がある。
- 自動起動の見直し:スタートアップアプリを整理し,スワップへの落ち込みを防ぐ。
よくあるつまずきと回避策
- Wi-Fiが不安定:初回は有線LANで入れて,更新後にドライバが安定するケースが多い。
- スリープ復帰で固まる:省電力設定を緩める,カーネルやファーム更新を待つ。
- 古い周辺機器:プリンタ/スキャナは明確に“動作させたい型番”があるなら事前に検索。代替としてPDFワークフローへの切り替えを検討する。
- 32bit機の持ち込み:非対応。潔く対象外にしてトラブルを避ける。
まとめ:Ubuntu LTSは“ブラウザ中心生活”の強い相棒
いまは多くの作業がクラウド化されている。Gmail,Googleドキュメント,Microsoft 365のWeb版,Zoom/Meet,YouTube,学習プラットフォーム,家計やメモのWebアプリ……この領域ではUbuntu LTSは十分以上に戦える。逆に,Officeの高度機能や業務システムがWindows前提なら,Linux化を目的化せずデュアルブート/別PC併用で割り切るのが賢明だ。
“捨てる同然のPC”が手元にあるなら,Ubuntu 24.04 LTSを入れてまずはクラウド用の2号機として蘇生させてみてほしい。軽量フレーバーを選べば世代の古いIntel機でもまだまだ現役復帰できる。サポート期間と用途の相性だけ押さえれば,コストはほぼゼロ,得られる価値は大きい。